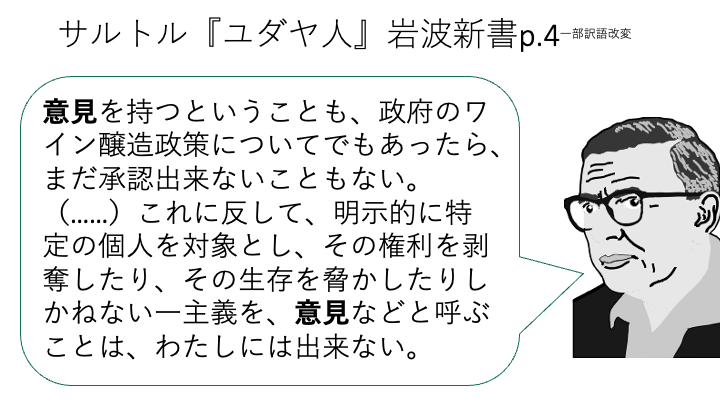閏月社から出版された『竹内芳郎 その思想と時代』という本に、「竹内芳郎とサルトル──裸形の倫理」という論文を書きました。
honto.jp
本日、この本の合評会シンポジウムが開かれます。
以下、拙論の要約と、今日話せたら話そうと(全部は無理と思いますが)思っていることです。
***
竹内芳郎という思想家の最初の著作は、1952年の『サルトル哲学入門』(後に『サルトル哲学序説』と改題)です。当時はサルトルの翻訳もほとんど出版されておらず、早い時期に非常に正確にサルトル哲学を解説したこの本(と同時に単なる解説書ではなく竹内の強烈な個性がすでに現れている竹内の代表作の一つです)は長い間サルトル哲学の定番の解説書でした。その後独自の思想を確立した竹内は多数の著作を発表したのですが、かつては多くの人に読まれていたものの、最近はあまり読まれなくなりました。竹内芳郎、今は名前も聞いたことがないという人も多いのではないでしょうか。サルトルの方は、読んだことはなくても名前くらい知ってる人は多いと思います。ところが、実はある時期からサルトルは「読まなくてもいい哲学者」扱いされ、「軽視」、あるいは「無視」されるようになりました。私がサルトルで卒論と修論を書いたころ、デリダ、ドゥルーズ、フーコーなど「ポストモダン」の思想が流行りで、当時私は「なんで今どきサルトル?」と何度も言われました*1。また「サルトルやるにしても今どき竹内芳郎でもないでしょう」みたいなことを言われたこともあります。
「軽視」の例としては、例えば内田樹は、2008年にブログでこう書いています。
私はサルトルの著作のうちで今日でもまだリーダブルなものはきわめて少ないと思う。そのあまりにクリアカットでオプティミスティックな歴史主義から人間についての深い理解を得ることは(少なくとも私には)ほとんど不可能である。(http://blog.tatsuru.com/2008/01/15_1150.html)*2
「無視」の例としては、「まなざしの地獄」の例があります。「まなざしの地獄」とは、社会学者の見田宗介が1973年に発表した有名な論文なのですが、2008年に河出書房新社でこの論文が単行本化された際、社会学者大澤真幸による長い「解説」が付されました。いうまでもなく同論文はタイトルからしてベタにサルトルです。後述するように「まなざし」は『存在と無』に由来するサルトル用語ですし、「地獄」は、サルトルが『存在と無』の他者論を演劇化した「出口なし」の最も有名なせりふ「地獄とは他者のことだ」から来ていることは間違いありません。さらに、内容も、明らかにサルトルの『聖ジュネ』が下敷きで、要所で同書の引用さえあります。ところが、大澤の「解説」には、一言もサルトルへの言及がないのです。そんな大澤が、2018年には朝日新聞で「往時の影響力を思うと、サルトルの忘却のされ方はすさまじい。私の考えでは、それは、サルトル後の世代の思想がひそかにサルトルを羨み、彼を乗り越えようとしたことの皮肉な結果である。彼らは『サルトルはもう終わった』かのようにふるまったのだ」などと言っているのですが、それはご自分のことを言っているのかな?と逆に驚いたものです。
さて、では、サルトルも竹内も本当に「昔は読まれたが時代遅れになった哲学者」なのでしょうか?しかし私は、両者はそもそもまともに読まれ受け止められたことがなかったのではないか、と考えています。
「サルトル」「実存主義」というと、「主体性」を強調する哲学、というイメージを持つ人も多いと思います。「ポストモダン」と言われる思想を評価する人々は、サルトルを近代的な「主体性」の哲学の典型だ、と言って盛んに批判しました。拙論では、桜井哲夫の『知の教科書フーコー』(講談社、2001年)を例に上げましたが、そこで桜井は、サルトル哲学を、フーコーによって批判された「近代的主体信仰」の典型だ、と言っています。
ところが、竹内は、まったく逆に、サルトル哲学を「近代的自我主義の超克」をめざした哲学だと言っていました。竹内によると、サルトルの哲学は「偶然性」と「出会い」の哲学でした。竹内はサルトルが1934年に書いた「自我の超越」という重要な論文を、原文も入手困難だった1957年にいち早く翻訳しているのですが、後年この論文についてこう書いています。
〔『自我の超越』は〕近代西洋哲学の根底にある自我主義(事実上の独我論solipsisme)を超克するための最初の、しかもはなはだ独創的な試み(の一つ)だった。
(竹内芳郎「『自我の超越』における《近代的自我》超克の試みとその現代的意義」、サルトル『自我の超越・情動論粗描』竹内芳郎訳、人文書院、2000年所収、7頁)
サルトル哲学のこうした側面、またそこに注目する竹内のサルトル読解は、サルトルの支持者からも批判者からも見落とされてきたのではないでしょうか。
***
「ポストモダン」から集中砲火を浴びたサルトルですが、竹内芳郎は、のちに「ポストモダン」思想批判も盛んに口にするようになります。竹内は、1980年代以降、日本社会の根底にある「集団同調主義」を「天皇教」と呼んで一貫して激しく批判し続けましたが、「ポストモダン」批判もその一環でした。彼は、日本で「ポストモダン」の名のもとになされていた「近代批判」「主体の哲学批判」が、新しい意匠をまとっているが、結局は「馴れ合い的」な人間関係にすぎない「共生」の肯定に帰着するとして批判しました*3。実は、竹内の「馴れ合い」批判の立場は、デビュー作の『サルトル哲学序説』から一貫していました。80年代以降の竹内がそれと闘おうとした「集団同調主義」「天皇教」は、『サルトル哲学序説』で「日本的現実」と呼ばれているものと同じです。同書で竹内は、サルトル哲学を「愚劣な日本的現実と闘う武器として生きる」と言っています。
ところで、「集団同調主義」と対立するものを、竹内は「裸の個人」と呼びます。しかし「裸の個人」とは「近代的自我」のことではありません。それは、共同体からはじき出された、「構造からのはみ出しもの」、アウトサイダーなのですが、竹内はこの「裸の個人」について世界宗教成立の場面まで遡ります。竹内は、1981年の『文化の理論』でこう言っています。
人権思想とは、人間の尊厳はその社会的役割なぞにはなく、かえってそれを脱ぎ棄てた裸のままの個体の存在そのものにあるとするもので、このようなかたちで個体が個体としての自覚に達するためには、個体が裸形のまま直接に超越的普遍者のまえに立ち、それによって普遍的価値を分与されるという、世界宗教のもつ、以前にもましてはるかに広大な社会的想像力(……)の発動が、その不可欠な媒体となったわけである。(竹内芳郎『文化の理論のために』岩波書店、1981年、269頁)
つまり、社会から排除されたアウトサイダーこそが、世界宗教(竹内は後にこれを「普遍宗教」と言い換えます)を作り上げ、いわば「神の前での平等」という発想を得たときに、普遍的なものとしての人権概念が人類史の中で初めて生まれた、というわけです。竹内は1990年にこのように言っています。
私が集団同調主義や天皇教を超える道として、「裸のままの個人」の発見やそれを支える超越性原理を語ったのは、なにも近代的意味での「個人主義」の確立なぞに突破口を求めてのことではなく、むしろ普遍宗教の「初心」に一度たち帰ることの慫慂(しょうよう)として語ったのだ(竹内芳郎『天皇教的精神風との対決』三元社、1999年、169頁)。
竹内は「人権」や「普遍性」を擁護し、「ポストモダン」的なものを批判するからといって、「近代的自我主義者」に鞍替えしたわけではありません。彼はむしろ、「ポストモダン」を標榜する人々の「相対主義」によっては、近代は乗り越えられないと考えます。近代を越えるためには「普遍をして真に普遍の名に価するまでに普遍化する途を追求すべき」なのであり、「近代が一般化したその普遍的原理を、近代とか西欧とかの制約を完全にのり超えるまでに普遍化する以外に途はな」い、と竹内は言います(竹内芳郎『ポスト=モダンと天皇教の現在』筑摩書房、1989年、139頁)。
***
竹内は、1989年に「討論塾」という場を創設します。これは今流行りの哲学カフェのはしりのようなものに見えますがしかし中身はまったく違います*4。彼はアカデミズムそのものから距離をとり、討論塾での市民との対話を主な活動の場としていきます。竹内は、ある時期から、サルトルに対してはむしろ批判的になり、サルトル論もほとんど書かなくなっていたのですが、討論塾の対話記録を読むと、晩年の彼は重要なところでサルトルに言及しています。竹内は「人権」をめぐる議論の中で重要な部分でサルトルの倫理学思想に言及しています。また2000年代には、「ポストモダン」の立場だと自称する討論塾の参加者と激しく論争する中で、彼は「ポストモダン」の主張は、ポストモダンによって「近代主義の典型」として弾劾されたサルトルがとっくに言っていたのだ、と指摘しています。たとえば、サルトルは、ポストモダン思想家に先立って「近代の自我主義、自我の論理一貫性=自己同一性の追求」をいち早く批判していたということ、また、サルトル哲学の実存的倫理の核心は、「他者のまなざしの敢然たる受容」をつうじた「自己脱出」「自己変革」だったということ、さらには、主体もその思想も常に「状況」においてあることはポストモダンに先立ってサルトルが強調したということ(だからこそ彼の評論集は『シチュアシオン』と題されていました)などです。つまり竹内は、「モダン」の立場から「ポストモダン」に反論したのではなく、むしろ近代の超克を志向するからこそ、ブームとなった「ポストモダン」思想の不徹底・欺瞞性を批判したのです。その意味で、竹内思想の根底には、「近代的自我主義の超克」を志向する、いわば「ポストモダン哲学としてのサルトル哲学」が最後まであり続けた、といえるのです。
***
竹内の文章には独特の「柔軟さ」があるとも言えます。澤田直が言うように、彼の最初の著作は、『サルトル哲学入門』と銘打っておきながら、63頁になるまで本文に「サルトル」が出てこない、とか、「即自存在」「対自存在」はサルトル哲学の概念なのに、まるで竹内が考えたかのように「「即自存在」と名づけておこう」とか「「対自存在」と名づけよう」と平気で書いてしまうところとか。これは澤田が言うように「現在のアカデミック・ルール」からは考えられないことですが、竹内はそういうところはあまり気にしなかったのかもしれません。この本では、サルトルの思想が「竹内という身体に取り込まれ、竹内の声を通して語られる。竹内とサルトルはほとんど一体化している」(『竹内芳郎 その思想と時代』72頁)とも言えますが、悪く言えば、「いい加減」ともとられかねません。
拙論で冒頭に取り上げましたが、谷口佳津宏は、サルトルを哲学書として「厳しく」(ストイックに)読むべきだ、という主張で、竹内を、その対局にある読み方として批判しています。谷口によると、竹内をはじめとする従来のサルトル読解は、サルトルを「日本的現実と闘うための武器として使う」などという「下心」があるから、サルトルの哲学書を(哲学と関係ない?)社会運動などにおける主張のために都合よい読み方をして使ってきた、と批判しているのだと思います(『竹内芳郎 その思想と時代』95−6頁)。
しかし、竹内思想には、まったく別の意味での「厳しさ」を追求する面があります。竹内は、吉本隆明の『「反核」異論』(深夜叢書社、1983年)を明らかに念頭において、こう言っています。
思想的にも倫理的にもなんらの普遍性要求のないところでは、あまつさえこの要求をファシスト的だとしてはじめから拒否するところでは、特殊・多様性の尊重とか相対主義とか思想的寛容とかの美徳も、現に見られるとおりそのまま思想上のだらしなさと同義となり、このだらしなさはいつでも容易に、権力の押しつけてくる「問答無用」のファシスト的思想統制への屈従へと転化するほかはないからである(『具体的経験の哲学』岩波書店、1986年、113頁、強調引用者)。
「思想上のだらしなさ」を許さない「厳しさ」のようなもの、それが竹内の思想、あるいは文章にはあります。小林成彬は、本論文集収録の「日本で哲学をすること──竹内芳郎の〈闘い〉」の中で、「竹内の文体が持っている独特の明快さにも一抹の不安を抱く」とし、こう言っています。
サルトルに、「時代の証人」や「殉教者」といった側面があることもたしかだが、デリダがサルトルを論じた美しい文章「「彼は走っていた、死んでもなお」やあ、やあ」(«Il courait mort» : salut, salut)が的確に提示しているように、「救済」(salut)が同時に「やあ」(salut)というフランクな挨拶にもなるような硬軟を併せ持つ(或いはふざけた)ようなところもサルトルはもっているのであり、それは私にとってサルトルの大きな魅力である。竹内はサルトルの「柔構造」を捉えそこねてはいまいかという不満を持つ。(『竹内芳郎 その思想と時代』150頁)
この「柔構造」という言葉から思い出したのですが、最初の方で引用した内田樹は、2002年のブログで、彼が、高橋哲哉によって、加藤典洋とともに「ネオ・ソフト・ナショナリスト」と呼ばれ、批判されたことについて言及しています(http://blog.tatsuru.com/2002/03/14_0000.html*5)。内田は、高橋哲哉の論理を「正しい」と思っている、としつつも、「「正しい」けどその語り口がダメ」*6と言います。内田によると、加藤典洋は「「多様性」を容認する人だということが直観的に分かる」から支持できるが、高橋哲哉は「「正しさの均質性」というものを恐れていないような気がする」から距離を感じるのだということです。そして彼は、高橋による「ネオ・ソフト・ナショナリスト」という呼称の中に「ソフト」という形容詞が入っていることが、うれしい、と言って、こう書いています。
私は高橋哲哉が言うとおり、わりと「ソフト」な人間である。
でも「ソフト」であり続けることに身体を張る、という点については、けっこう「ハード」なのである。
ハードじゃないと生きていけないし、ソフトじゃないと生きてる甲斐がない。
マーロウさんもそう言ってるじゃないですか。
しかし、内田の「正しさの均質性への恐れ」とか「多様性を容認するソフト」とは、それこそ竹内が批判した、「普遍性要求を要求をファシスト的と拒否する」吉本的「思想上のだらしなさ」そのものではないか、と思います。拙論で最後の方に書いたのですが、2000年代に討論塾では「ポストモダン」をめぐる激しい論争が行われています。その中で、「ポストモダン」の立場に立つある討論参加者が、自我の論理一貫性=自己同一性を追求することは、かえって自己抑圧的であること、「場」や「状況」を重視したことが「ポストモダン」の思想的意義であると主張しています。この参加者は、左翼の集会では「君が代・日の丸」反対の決議に賛成しながら、卒業式で着席を貫けなかったり、職員会議で反対が言えなかった教員の例をあげ、論理的一貫性や自己同一性を保とうとすることはかえって自己抑圧的になる、というのです(『竹内芳郎 その思想と時代』105−6頁)。この人は、やはり竹内的「厳しさ」を抑圧的と感じていたのではないでしょうか。そして、生活者の一貫性のなさ(だらしなさ)を、いわば「柔構造」として評価し、それが「ポストモダン」の思想的意義だと考えているようです。これに対して竹内はどのように応答しているのでしょうか。このポストモダンの人が上げていた、信念を貫けなかった教員の例について、竹内は教師が教育の場で自己の良心や信念を貫けないようにしている社会の抑圧性を放任しながら「主体性」のもたらす抑圧性のみを問題にすることの滑稽さを指摘すると同時に、自分であれば、左翼集会では、「単に反対決議に同調する代りにそれが孕む数々の問題点(……)を公然と呈示するように努め」逆に職員会議では、「反対する教師の良心の自由を尊重することが教育活動にとって如何に不可欠かを訴える」だろう、と反論しています。つまり、よく読むと、実は、信念を貫く竹内的教員こそが、状況に応じた対応を行う柔軟さを持っているのです。竹内は、「常に場の中から倫理を発想すること」と「常に場に働く力に屈服すること」とは全く別のことであり、「状況の中の思想」と「状況追随主義の思想」とを取り違えるべきではない、と言います。
サルトル思想は、確かに、「状況の中の思想」という「柔構造」を持っており、この側面は非常に重要なサルトル思想の核心です。ただ、それは、単なる「思想上のだらしなさ」、「状況追随主義」とは違う、ということは踏まえておかねばならないと思います。
***
ところで、青土社の雑誌『現代思想』2021年11月号「特集=ルッキズムを考える」では、既述した見田宗介「まなざしの地獄」についても書かれた高島鈴の素晴らしい論考「都市の骨を拾え」(その後『布団の中から蜂起せよ』に収録されています)も含めて、「まなざし」という言葉が複数の論文・編集後記に計31回登場します。しかし、「サルトル」という言葉は一箇所も登場しません(サルトルと関係の深いメルロ=ポンティ、ファノンは登場します)。「まなざし」という言葉はサルトルの『存在と無』を起源とするもともとは「サルトル哲学用語」であるにもかかわらず、です。岩波でも平凡社でもいいので哲学辞典で「まなざし」の項目をひいてみてください。どちらにも「まなざし」はサルトル哲学に由来する言葉だと明記されています。「まなざし」という言葉は思想系の文章でいまもよく使われますが、これがサルトル哲学に由来する言葉だとそもそも知らない人も多いのではないでしょうか。これは、サルトル忘却現象の現れであるとも言えるでしょうか?たしかにそうとも言えます。サルトルはあまり「読まれ」なくなっているのかもしれません。しかし、これらの、ルッキズムを考える文章たち、すなわち、竹内の言う「日本的現実と闘う」文章たちの中に、サルトルは「生きられている」のではないか、とも思うのです。
サルトルが「生きられている」と感じたもう一つの例は、新宿梁山泊による、サヘル・ローズさん主演の『恭しき娼婦』の上演です。これは、サルトルが1946年に発表した、アメリカの黒人差別を告発する戯曲です*7が、ここでは、舞台が近未来の日本に改変されています。安田菜津紀は、この公演の観劇記の中で以下のように書いています。(kangaeruhito.jp/article/5713)
舞台設定は近未来の日本。サヘルさんはとある街にやってきたばかりの「娼婦」だった。そして男性たちの欲望と時代に翻弄されていく。(……)
「日本人」とは誰か?を改めて考える。日本国籍を持つ人? いや、日本国籍でも日本で殆ど過ごしたことがない、もしくは日本語を話さない人もいる。日本語話者? いや、外国籍でも流暢に話す人もいる。日本在住の人? いや、暮らしていてもルーツやアイデンティティは多様だ。では“日本文化”を愛する人……?
結局定義などできない空虚なもののために、人を無為に傷つけていく愚かさをまざまざと突きつけられたように思う。
サヘルさん自身、この舞台を演じることはどんなに苦しいことだっただろう。本来は多くの人々が問題提起しなければならないことを、彼女ひとりの肩に背負わせてしまったような気がした。だからこそ舞台を観せてもらった一人として、託された宿題をみなと分かち合わなければ。そんな思いでこの文章を綴った。観劇から2カ月近くが経ち、ようやく少し、言葉にできた。それほど壮大な問いかけの詰まった舞台だった。
サルトルは、どこかの「研究室」の中にだけではなく、こうした舞台や、様々なパンフレットやプラカード、演説*8、会話の中に生きている、そして生き続けているのです。最後に竹内のことがどこかに行ってしまいましたが……もちろん竹内思想も、です。